「冬の大根はいつまで収穫できる?」「霜が降りても大丈夫?」「収穫が遅れるとどうなる?」と心配になっていませんか?冬大根は霜が降りる前に収穫するのが基本ですが、地域や品種によってタイミングが異なります。
この記事では、現役農家が冬大根の適切な収穫時期から、収穫遅れで起こるす入りや根割れの症状、霜対策まで詳しく解説します。さらに、収穫後の大根を畑で長期保存する方法もご紹介。正しい知識で美味しい大根を無駄なく収穫し、冬の間も新鮮な大根を楽しみましょう。
冬大根の収穫時期以外の大根の育て方に関する情報もチェックされている方は「大根の育て方のまとめ」もあわせてご覧ください。
冬大根の収穫時期はいつまで大丈夫?
秋冬の大根の収穫時期の目安
秋冬の大根の収穫時期は、秋の種まきから60~90日頃です。
ただ、収穫までの日数は品種や地域によって違います。
立っていた外葉が垂れてきて、横に広がってきた頃が収穫の目安になります。

冬大根は霜が降りる前に収穫する
大根は、霜が降りる前までに収穫するとよいです。
霜が降りると、大根の水分が凍り、大根が傷む原因になります。
また、味と食感がよくなくなります。
特に、霜が降りやすい寒い地域では気をつけてください。
朝の気温が5℃以下だと、霜が降りやすくなります。
霜が降りたときは、霜が溶けるまで収穫しないようにしましょう。
朝ではなく、午後の暖かい時間に収穫するとよいです。
霜が降りる時期は、地域によって異なります。
北海道や東北などの寒冷地では、平年は10月下旬~11月中旬頃です。
関東や西日本などの温暖地、暖地では、11月~12月にかけてになります。
霜の被害を減らすには、もみ殻やわらを敷くとよいです。
また、マルチやトンネルも有効です。
暖地や温暖地では、大根の首元に土をかぶせることで、冬の間畑で保存することができます。

冬大根の収穫時期|遅れるとす入りなどの症状が出る
大根の収穫が遅れると、「す入りする」、「根が割れる」などの症状がでます。
大根の収穫に遅れないためには、収穫時期の前に試しに数本抜いてみるとよいです。
大根の冬の収穫時期に遅れると|す入りして味が悪くなる
す入りとは、根の内部に空洞ができ、スポンジのようにスカスカの状態になることです。
味がしなくなり、食感はぱさぱさします。
す入りが起こる原因は、大根の老化や水分不足です。
根が大きくなるのに対して、細胞が育たなくなり、大根に空洞ができます。
大根の品種には、す入りしにくい品種があります。
す入りしにくい品種を選べば、収穫が遅れてもす入りする確率が低くなります。
す入りした大根は、水分が少ないため生で食べてもおいしくないです。
そのため、サラダには不向きです。
水分を抜いて作る漬物や切り干し大根にすると、おいしく食べられます。
味が染みこみやすいので、煮物もおすすめです。

大根の冬の収穫時期に遅れると|根が割れることがある
収穫が遅れると、根が割れることがあります。
根の表面の成長がだんだんと遅くなり、根の肥大に追い付かなくなることで起こります。
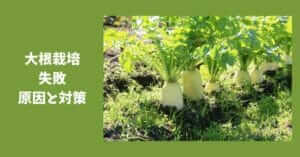
大根を冬の収穫後に畑で保存する方法
冬に収穫後の大根を畑で保存する方法を紹介します。
大根を土に埋めることで、冬の間保存することができます。
まず、収穫した大根の葉を切ります。
大根を埋められるだけの深さ(30~50㎝くらい)の穴を掘ります。
その穴に、葉を切った大根を入れます。
大根を入れたら、穴を土で埋めます。
寒冷地では大根が凍りやすいので、50~70㎝くらいの深さまで穴を掘ってください。
そして、下にわらを敷いてから、大根を入れるとよいです。
この保存方法で、早春まで保存できます。

大根の冬の収穫時期|まとめ
最後までお読みいただき、ありがとうございます。
大根の冬の収穫時期について、紹介しました。
大根の冬の収穫時期のポイント
・大根の収穫は霜が降りる前にする
・収穫が遅れると、「す入りする」、「根が割れる」などの症状が出る
・収穫後の大根は土に埋めて保存できる
収穫がうまくいけば、おいしい大根が食べられます。
ぜひ、がんばってみてください。
関連記事一覧
